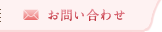ごあいさつ

近年の出生率の低下や高齢妊婦特に生殖補助医療の普及による高齢妊娠の増加傾向に伴い、出生前染色体検査や着床前診断への関心と期待が高まってまいりました。
一方、分子遺伝学の目覚ましい発展とともに臨床遺伝学も新しい展開を遂げています。
しかし、出生前染色体検査を含む出生前診断や着床前診断は胎児生命を尊重することなど多くの倫理的問題を含み、軽々しく行われてはいけない医療であり、また、その結果により胎児生命が左右される重大性を孕んでいます。
私どもはこの点に配慮し、各産婦人科医師、臨床検査技師、細胞遺伝学者らが各々の分野に責任を持ち情報を共有しながら、正確で問題の起こらない検査・診断を目標としております。
また、染色体検査、遺伝子検査の倫理的、社会的問題、及び遺伝学的フォローアップの重要性に鑑み、当センターでは日本人類遺伝学会及び日本遺伝カウンセリング学会により認定された臨床遺伝専門医がすべての面で統括した体制で進めております。
DNAプローブを用いた蛍光 in situ hybridization(FISH)や SNP micro-arrayなど最先端の検査技術を駆使し、他の施設よりも迅速で、かつ正確な報告をお約束致します。
社員一同、お母様方と諸先生のご要望にお応えすべく新しい技術の開発にも積極的に取り組んでいく所存です。宜しくご支援のほどお願い申し上げます。
(有)胎児生命科学センター
Fetal Life Science Center
取締役
鈴森 薫 (名古屋市立大学名誉教授、日本産科婦人科学会専門医、臨床遺伝専門医・同指導医)
副社長
孫田 信一 (臨床細胞遺伝学認定士・同指導士、理学博士)
出生前診断に関する基本的な考え方
出生前診断は、施行時期により妊娠初期(妊娠9~11週)の絨毛診断と妊娠中期(妊娠15週~17週)の羊水診断に分けられますが、更に診断目的によって染色体異常の診断と遺伝子病の診断に分類されます。
出生前染色体検査では胎児の一般的な染色体異常はすべて判明します。
出生前染色体および遺伝子診断は、以下のように、その適応がはっきり決まっています。
(1)重症の遺伝性疾患(染色体異常症や致死的または治療法が全くないような遺伝子病)の子供を既に有している場合
(2)染色体異常児を心配している高齢女性
(3)親が染色体異常の保因者である場合、等
出生前診断は、倫理的問題点を少なからずもっています。また、医師自体がこの診断を間違って運用したり、診断結果の誤った解釈のもとに誤った説明をすることもあり得ます。この意味で、出生前診断は倫理的のみならず社会的にも責任を持つことになります。そのため、日本産科婦人科学会及び日本人類遺伝学会では出生前診断に関するガイドラインを設けていますが、私どもはそれでも不十分だと考え、出生前診断は以下のようなシステムのもとにのみ行われるべきだと考えます。
1)出生前診断は、発端者の主治医、産婦人科医、細胞遺伝学者、分子遺伝学者、遺伝カウンセラー、精度管理に信頼の置ける細胞・分子研究施設のネットワークで行うこと。このうちで欠けてならない専門家は遺伝カウンセラーです。無論これらの人はオーバーラップすることがあります。産婦人科医であって、細胞遺伝学を修め、且つ臨床遺伝学に造詣の深い医師はこの例です。また、これらの担当者間にフィードバック機構があり、技術の向上や情報の交換、あるいは暴走を防ぐためのチェック機構の存在も重要です。
2)上記の各担当者間での責任を明らかにすること。例えば、出生前診断に関する医療上の責任は主治医あるいは産婦人科医にあり、細胞・分子遺伝学的診断結果の責任は検査センターにあり、その遺伝学的説明に関する責任は遺伝カウンセラーに存する旨の確認・誓約を行うことが望ましいと考えます。
3)倫理的・道義的問題点を勘案し、出生前診断の適応を遵守して行うこと。倫理的には、人権に関する「ヘルシンキ宣言」を遵守することにつきますし、適応は上述の通りです。具体的には、性別判定は出生前診断の適応にならないことは当然ですし、治療法がある遺伝性疾患も適応になりません。また、よしんば出生前診断の結果、胎児の性別が判明しても、それは「親に伝えるべきでない」というのが世界中の鉄則です。
4)出生前診断は親の強い希望で行われるのが通常ですが、深い信頼関係にある医師の下で、且つ十分な経験のある医療機関のみで行われるべきです。
5)上記の原則から大きく外れる場合は検査を行わないこと。通常の臨床検査とは意味合いが大いに異なることは既述のとおりです。